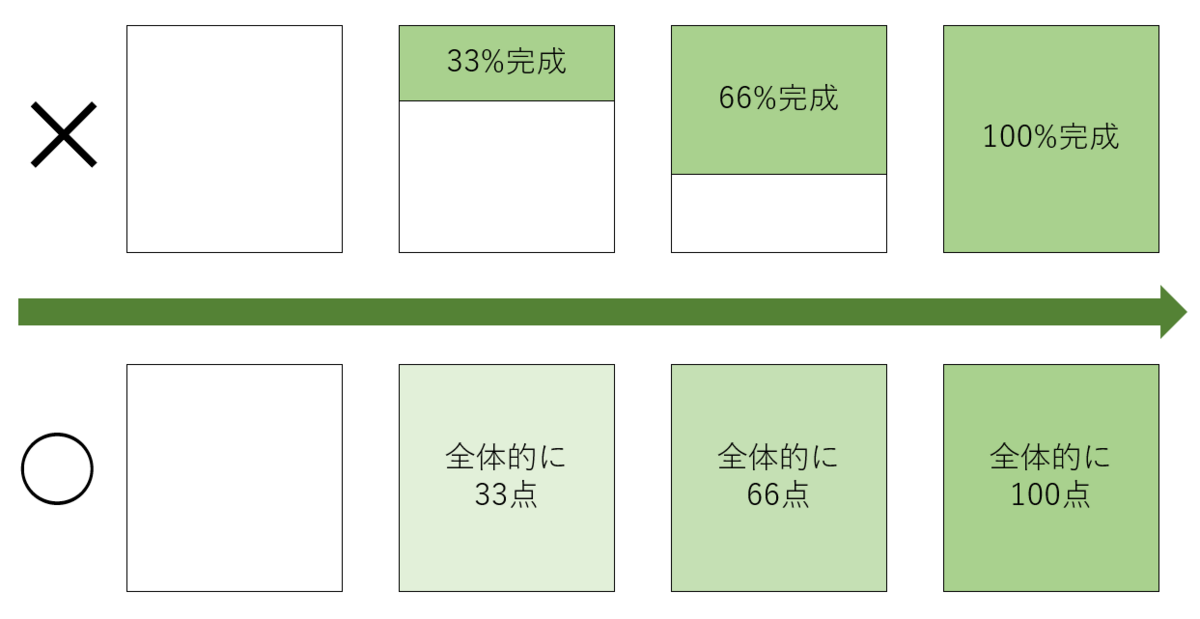オタクのブログです。
/* メモ
トップ記事更新:24/7/21
2020年4月以降の記事は全部載せたがそれ以前の記事は絞っている
人気記事に★マークつけた
*/
■『魔法少女七周忌♡うるかリユニオン』掲載中
あれから七年、皆が魔法を拗らせた。
元魔法少女と元敵幹部が再会するガールミーツガール。
■アニメ・映画感想
ボーはおそれている
16bitセンセーション
君たちはどう生きるか
★ぼっち・ざ・ろっく
★リコリス・リコイル
ウマ娘 プリティーダービー Season2
★劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト
★シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇
Re:ゼロから始める異世界生活(第2期前半)
遊戯王ZEXAL
仮面ライダー555
傷物語
ウォッチメン
プリンセスコネクト!Re:Dive
遊戯王5D's
PSYCHO-PASS
アキハバラ電脳組
ソードアートオンライン
バットマンvsスーパーマン
マギアレコード
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
アズールレーン
劇場版ハイスクールフリート
異種族レビュアーズ
★パラサイト 半地下の家族
ドラえもん のび太と鉄人兵団
マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)
Re:ゼロから始める異世界生活(第1期)
オーバーロード
グランベルム前・後
ジョーカー
トイ・ストーリー4
遊戯王ARC-V
通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか?
魔法少女なのはストライカーズ
クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲
★遊戯王GX
八月のシンデレラナイン
バーチャルさんはみている
輪るピングドラム
■漫画・ラノベ感想
★ダンジョン飯
鉄鍋のジャン
死亡遊戯で飯を食う。
★東京卍リベンジャーズ
進撃の巨人
二月の勝者
がっこうぐらし
サムライ8
進撃の巨人
ワールドトリガー前・後
ワンピース
■お題箱
161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/
151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/
141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/
131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/
121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/
111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/
101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/
91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/
81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/
71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/
61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/
■消費コンテンツ
2024年 2~3/4/5~6/7
2023年 1/2/3/4~6/7~9/10~翌1/
2022年 1~2/3~4/5/6~8/9~11/12/
2021年 1/2/3/4/5/6/7/8~9/10~12/売却コンテンツ1・2/
2020年 4/5/6/7/8/9/10/11/12/2020春アニメ1・2/2020秋アニメ/
■創作活動
『魔法少女七周忌♡うるかリユニオン(うるユニ)』あとがき
『席には限りがございます!(にはりが)』解説・大反省会1・大反省会2
『ゲーミング自殺、16連射アルマゲドン(ゲーマゲ)』解説
『皇白花には蛆が憑いている(すめうじ)』解説
『Vだけど、Vじゃない!(VV)』
■サイゼミ
1/2/3/4/5前・後/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/
■理系トピックス
データサイエンティスト業務用リハビリ書籍感想
★データサイエンス系資格だいたい全部取った
データサイエンスエキスパート攻略
『入門 統計的因果推論(Judea Pearl)』メモ
統計検定1級とかいうゲームに勝利した
複雑ネットワーク科学入門書籍の感想
竹村彰通『新装改訂版 現代数理統計学』の感想
ポインタと確定記述、変数名と固有名のアナロジーについて
機械学習入門書籍レビュー
■その他
★東大卒無職のTwitter就活記
カードゲーム『CROSS GEAR』紹介/解説1・2・3・4
★マジでカードゲーム強い人たちにマジで強くなる方法聞いてきた
2023年買って良かったもの
★「生成AIの『学習』は学術用語だ」ということをそろそろちゃんと説明した方がいい
2023俺が選ぶ歌い手ベスト10
★就活に苦しむインテリの学生に社会の真実を教える
★『粛聖!!ロリ神レクイエム☆』はロリコンソングではありません
中学生ぶりにラノベ熱が再燃したので女性主人公ラノベレビュー1・2
「入間人間の手口がだいぶわかってきた」って何やねん
1秒もプレイしてないNIKKEキャラデザ真剣評価
重い腰を上げて10年前に積んだ女性主人公ラノベ83冊を崩した1・2・3・4
AI挿絵付きWeb小説を投稿し始めて2ヶ月経った話
★君はAI創作の最前線にして最底辺「AI拓也」を知っているか
プランナー目線の生成AI妥協論
何故AIにはイラストを発注できないのか?
★小二で全国模試一位を取った男の半生・延長戦
人生で初めて歌ってみたに激ハマりしてる話
2021年買ってよかったもの
白上フブキは存在し、かつ、狐であるのか:Vtuberの存在論と意味論・延長戦
ゲートルーラーは「本物」かもしれない
表紙が三枚あるノートを特注した話
ロラン・バルト『物語の構造分析』メモ 構造分析vsテクスト分析
プライムデーセールでKindle端末を買うべきか?
『Vだけど、Vじゃない!』:Vtuberはどこにいるのか?
ダブルマスターズドラフト攻略
倫理は永井均しか勝たない
ポストモダニズムから資本主義リアリズムまでの間に何があった!?
『リアリティーショーを批判しているオタクもVTuber見てんじゃん』を受けて
ハッシュタグの氾濫、メタ政治性を巡る闘争
100日後に死ぬワニはなぜ失敗したのか
オタクの中韓コンテンツ張り
『ダンベル何キロ持てる?』を見たオタクが3ヶ月筋トレした結果……
日本興行収入上位映画100本を見た感想
実用系アニメのポテンシャルを評価せよ
ガチャを叩く時代は終わった